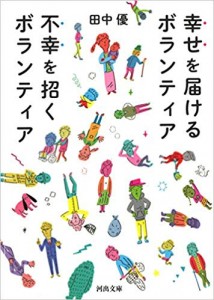
◆なぜこの本を読もうと思ったのか?
食フェスでボランティアスタッフを集おうと考えている。しかし、自分がボランティアをしたことがないし、しようとしたこともないため「ボランティアをする人の動機は何なのか?」が知りたくなったから。
◆著者の言いたいこと
ボランティアとは「無料で働く」ことではなく、「自発的なもの」であると著者は言う。小学校で行われる「ゴミを拾いましょう」などというものは、半強制的なものであってボランティアではない。そして、自発的かつ自分の意志の押し付けであってはならない。使わない古着がたくさんあるから世界で困っている人に送ろう というのは短絡的である。古着を送ることによって、現地の繊維業といったような軽工業が発展しないままになってしまうからだ。幸せをとどけるボランティアをするためには、相手の状況を思いやることができるのか?が非常に大事である。
◆本を読む前の疑問点と読んだ後の回答
Q1.ボランティアをする人たちって何が楽しいんだろう?動機は?
→A1.必要とされることによって、自分の存在価値を実感することができる。
Q2.ボランティアをしたい人たちに響く訴求ポイントは何だろう?
→A2.①自分が活動することが社会的な「何か」に貢献しているという実感 ②直接的に言われる「ありがとう」→承認欲求が満たされるから。 ③
◆本を読んだ後の疑問点と予想される回答
Q1.ボランティアをする対象というのは、自分よりも劣っている人?困っている人?食フェスのような恵まれている人に対しては?
◆自分オリジナルの見解
起業をする人とボランティアをする人では、根本的に考えが違うのか?と考えいてたが共通点があると感じた。誰かに何をして貢献したい!という思いと、その対価を欲しがる点が共通している。しかし、その対価をお金で得ようとするのか、「自分という存在が誰かの役に立っているという実感」を得ようとする点が違う。著者のように、ボランティアを極めている人はともかくボランティア初心者の人たちが求めているのは金銭的な報酬ではなく、「お金の報酬は頂いていないのにこんなに大変なことを自らやっている」という実感なのだ。
したがって、主催する食フェスをする際には
①あなたという存在や活動がどう役に立つのか?(個人の現場の承認欲求)
②ボランティアの活動全体がどう社会的に意義があるのか?(個人の大義名分)
をポイントに訴求できれば良いと思う。
「九州産のにんにくを日本全国・世界に広めよう!」というテーマが良いのではないか?
しかし、なぜ九州産のにんにくを広める必要があるのか?という情報が足りない。その疑問への回答を用意する。
◆今後勉強する分野
・NPO法人の立ち上げ方
・ボランティア団体の立ち上げ方
・学生団体の立ち上げ方
◆読書メモ
・小さいことでもボランティア
・自分もサッとしてあげた優しさで喜んでもらえたら嬉しい
・善意の押しつけをするところも多い→目立ちたがりのボランティア
・「どこどこの団体がやっています」と主張する
・誰かのなにかに貢献したい!という層がいる→ほしい対価はお金じゃない→自分は教育が仕事
・なぜお金をもらいたいと思わないんだろう?その活動は何で成り立っているんだろう?
・自分都合ではなくて、ボランティアをされる側の都合で考える
・著者は楽しくてボランティアを続けている
・苦しくてツライものだったら続けることができない
・【著者の意見】「いいことをする」というのは恥ずかしい
・【著者の意見】ボランティア活動は自発的なものであり、強制労働ではない。
・【著者の意見】実際にする行動と、大義名分が合っているかどうかが大事
・図書館ボランティアの例より、ボランティアが他の人の仕事を奪ってしまうかもしれない
・ボランティアが安い労働力として安易にりようされると、人々は逆に困る
・非営利団体は寄付で成り立っている
・NPOのスタッフは十分な給料をもらっていない→そりゃそうだ。笑
・こんな活動が必要だと思うからやっている。自分で資金を負担して。→なぜそこまでの動機が出てくるのか?
・市役所も人件費をタダにして浮かそうと思ってボランティアを募集する
・寄付でしか成り立たないから少なくとも立ち上げまでは自腹で用意する
・待っていたって誰も何もしてくれない。だから自分がやる、という精神。
・実際は、財力と信用のある市役所に人が集まる
・支援してあげたいと思うのなら、お金はないけれど大切な活動をしている団体を手伝うと良い。それがボランタリー(自発的)な意識。
・日本人の特性として豊かな人が貧しい人に恵んであげるのは普通
・街頭募金での詐欺もある
・募金で集めた金額のうち何割を実際に送らないといけないという法律がない
・楽しくないボランティアはすべきでない
・ボランティアの人が楽しむために→楽しいことを見つける
・著者は、本の印税や講演会で収入を得ている
・家事の手伝いもボランティア?言われてからやるよりも、言われる前にするとありがとうが嬉しい。
・金銭的な報酬でしか動いていなかったけれど、そこじゃないんだな。
・褒められたい、いい人に思われたいという動機から始まっても良い
・ボランティアをしている人たちの間にいると、いいことをしている感じがなくなる。→もっと大変なことを楽しそうにしている人たちがたくさんいることを知るから
・自分が人の役に立っている、こんな自分でも誰かの役に立っている。と実感がもてる。サラリーマンの人はやりたくない仕事をしてお金をもらっている。でも、ボランティアの人は楽しいことをしている。それは誰かからのお金ではなくて承認欲求。
・ボランティアをする側が助けられる。愛情に恵まれていると承認欲求は満たされている。恵まれていない人に訴求
・ボランティアは自分の安心感のためじゃなくて、本当は相手のため。食フェスでいうとお客さんのため。
・おじいちゃんの例:存在価値を確認できるから、人は生きれる。→これは同じ。そういうことなのね!
・ボランティア活動をした人は、より深く考える人になる
・キャリアアップのためだけにボランティアをする人もいる。そういう人たちにとっては、ボランティア先の人々は自分のための道具でしかない。
・誰かをボランティアして助けるつもりで居ながら、誰かに助けられていては元も子もない
・支援をすることがかえって自立を妨げることがある
・ワンダラー小僧:1枚1ドルといって絵葉書を販売する途上国の子ども。1日頑張って大人が働いても1ドルなのに、1枚で親の収入を子どもが越えてしまう。だから、親が働く気がなくなってしまう。
・古着をおくることによって、現地の軽工業が発展しない。中古自転車を送ることで、自転車やが潰れる。
・2001年のアフガニスタンには、何も無かったのでそういうものが必要なときだった。→現地の状況によってかわる
・ボランティアで大事なのは、いかに相手の状況を思いやることができるのか?である
・カンボジアの難民キャンプにいる人は、食料もあるし保育器もある。外にいるタイ人の農民は貧しいまま。
・難民キャンプって非常に厳しい場所。それでもやろうとする人がいる。
・災害ボランティアに参加した人たちは、自分が毎日必要とされることに感動を覚える→普通の社会に戻れなくなる
・ボランティアで、依存する、依存させる状況を作り出してしまう。
・ひのきの例:明らかに自分が得ではないということがわかっていて、誰かに役に立つのがわかる これに共感するのか?
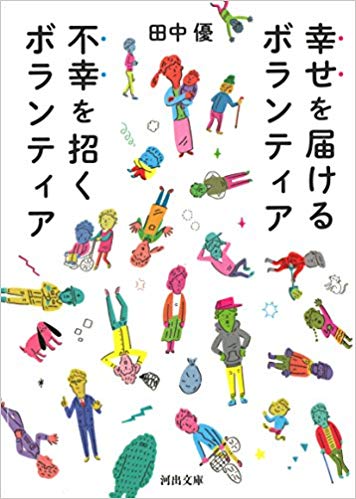

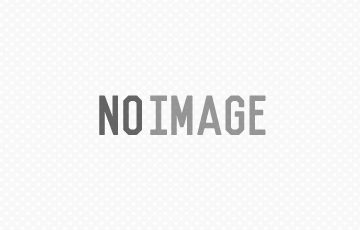
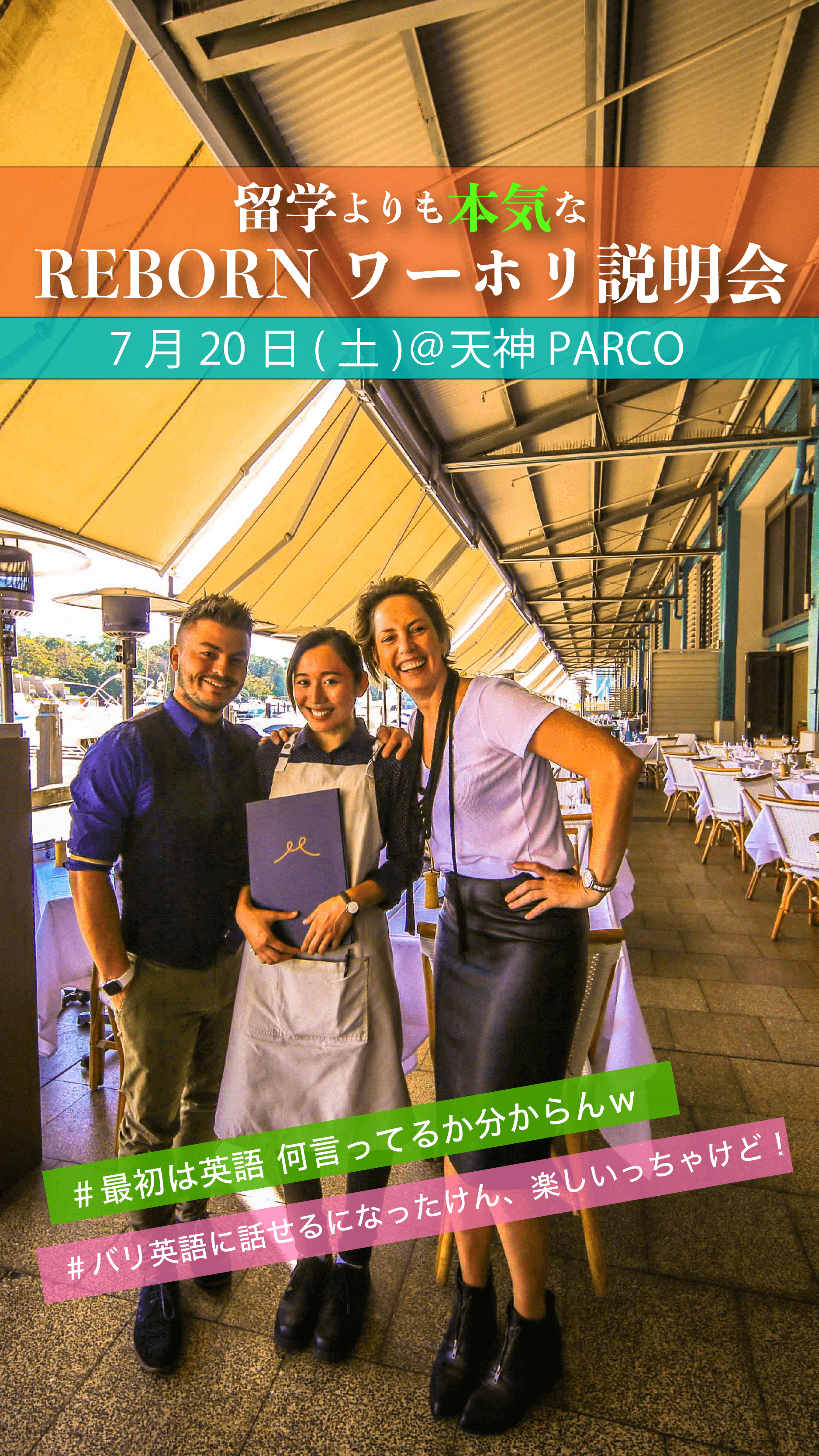
コメントを残す