ニュース概要
確定拠出年金、65歳まで加入延長を検討 厚労省
厚生労働省は運用成果によって年金額が変わる確定拠出年金について、掛け金を払い込める期間を延ばす方向で検討に入る。上限を60歳から65歳に上げる案が軸だ。期間が延びれば、老後に受け取る年金は増える。60歳を超えても働く人が増えているため私的年金の仕組みを充実させ、先細りする公的年金を補う。
このニュース記事の目的
確定拠出年金のことを正しく理解し、自分はどういう選択をすればいいのか決める
調べた情報
【確定拠出年金とは?】
日本の年金は3階建てである。
1階:国民年金
2階:厚生年金(サラリーマン・公務員)国民年金基金(自営業・フリーランス)
3階:確定給付企業年金(企業が積立)・確定拠出年金(個人が積立)
確定給付企業年金は、掛け金を金融機関(生命保険会社や信託銀行)が運用し将来ある程度確約された年金がもらえる。
確定拠出年金は、掛け金を自分の個人口座に積み立てて自分で運用し、将来もらえる給付額は運用の仕方による。
【確定拠出年金で将来に給付される年金は3種類】
1)老齢給付金:減速として60歳から年金、または一時金として給付される
2)障害給付金:高度障害時に年金、または一時金として給付される
3)死亡一時金:死亡時に一時金として給付される
【確定拠出年金に入るメリットは?】
1)税制優遇措置が充実している
2)運用コストの安い投資信託商品が利用できる
3)企業型確定拠出年金の場合、社外に拠出金を積み立てているため倒産しても従業員の年金資産として保護される
・・・
1)税制優遇措置が充実している
①掛け金が全額所得控除の対象となる(個人拠出分)
サラリーマンは年間276,000円まで拠出することができ、全額所得控除の対象となりつつ所得税は年末調整で還付を受けることができる。
②運用益は非課税
一般の金融商品の場合、得られた利息に対して源泉分離課税(20.315%)が課せられる。確定拠出年金の運用で得た運用益は非課税でもらえる。
③受け取るときにも税務上のメリットがある
年金で受け取る場合 :他の公的年金と合算して、公的年金等控除が受けられる。
一時金で受け取る場合:退職金と合算し、退職所得控除が受けられる
出典:りそな銀行
【確定拠出年金のデメリットは?】
1)60歳まで引き出しができない
2)解約できない
3)年金運用を自分で行うので支払った年金より減る場合がある
・・・
3)年金運用を自分で行うので支払った年金より減る場合がある
確定拠出年金の掛け金で運用する場合、元本保証型と元本保証がないものと選ぶことになる。元本保証型は定期預金や、保険。補償がないものが投資信託。保険は、解約をするときに解約控除を差し引かれることがあり、その金額が運用して得た利息を越えると元本を割ることになる。定期預金の場合は、利息を上回る解約手数料は取られないが、毎月運用手数料が取られている。
仮設:自分だけが気づいた問題点・重要なポイント
公的年金で毎月引かれているお金は、国が運用しているのに対して確定拠出年金は自分で運用することになる。国よりも運用がうまくいけば公的年金よりも年金が確保できるけれども金融商品である以上絶対はない。保険、株、投資信託など金融商品はたくさん存在するけれども素人が知識のないまま誰か(企業の営業マン等)の言うことを鵜呑みにして手を出して良いものではない。
銀行のサイトには当然良いことしか書いていないが、大事なのは運用するための知識やスキルである。
自分ならこうする
確定拠出年金は、もともとの目的として公的年金だけじゃ将来の年金が心配だから設立されたものである。つまり、将来のための資産形成のための手段の1つである。自分の個人の収入のうち、使わないお金を貯金するのではなくどのように運用して資産形成をしていくのか?に関する知識を入れて、客観的に判断していく。現時点では、確定拠出年金は利用しない。なぜなら、①非課税である ②受け取るときにも控除を受けられる というのが魅力的に感じたが、①60歳まで受け取ることができない ②解約ができない(支払いのストップのみ。その間運用手数料はとられる)のデメリットの方が大きいからだ。自分にはもう少し裁量のある金融商品が良いと感じたため、別の記事で株や投資信託などのリサーチをしていく。
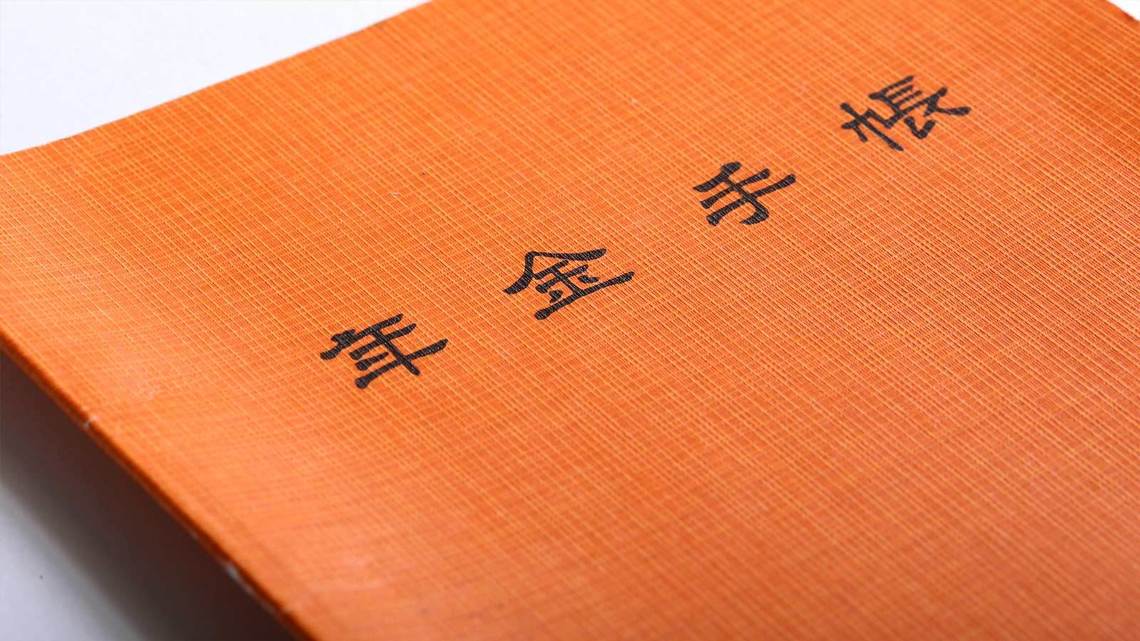
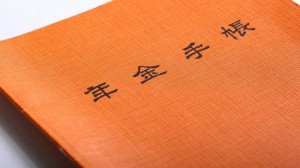

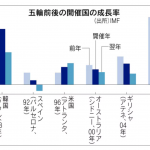


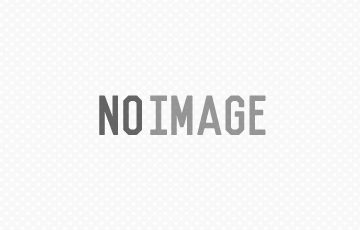




コメントを残す