
ニュース概要
経団連の中西宏明会長は3日に開いた記者会見で、就職活動の時期などを定めた「就活ルール」の廃止に言及した。国境を越えた人材の獲得競争が広がり、経団連が個別企業の採用活動をしばるのは現実に合わないとの意識がある。一方で安倍晋三首相は同日夜、採用のルールを守るよう改めて要請。学業への配慮を求める大学側との調整が進みそうだ。
このニュース記事を書く目的
将来的には自分の会社でも新卒を採用しようと考えている。ベンチャー企業としてどのように望んだらいいのか意思決定をする。
調べた情報
【背景】
ITなどの分野おける人材獲得で海外に遅れをとる。
【形骸化している就活ルール】
面接解禁日前に内定が4割。もともとは、企業や学生の負担を軽減させようと作られたもの。
【海外の就職活動】
技術や経験を元に何ができるのか?が評価をされるため、学生のうちからインターンシップを経験している。ドイツは例外だが転職をするのが普通なため、1つの会社にずっと雇ってもらおうとするのではなくその会社での経験を活かしてスキルを蓄積し他の会社へと移っていく。
自分だけが気づいた問題点・重要なポイント
就活のルールが廃止されることで、早期化し学業に支障が出るというのは関係がないことだろう。新卒一括採用という仕組みは、高度経済成長時代に作られたものであり当時にはぴったりだった。モノをとにかく作れば売れた時代だからこそ、何も知らない大学生を一度に教育をしてその会社で最後まで雇用するシステム。
問題なのは、企業側の「一度うちに来たらやめないで欲しいという考え」と学生側の「一度採用したら最後まで雇ってほしい」という共依存な考えだろう。大企業だろうが、中小企業だろうが魅力的な会社であれば学生はくる。学生も、何も知らない「まっさらな状態に価値がある」という風潮がずっと続くとは思わないほうが良い。
自分ならこうする
もし自分が今の知識をもって大学に入学するならば、1年生の段階から興味のある会社でインターンシップをする。企業が取り組みたいけれど、人手が足りずに手が回っていない仕事を担当して次のインターンシップで使えそうなスキルを身につける。大学での勉強も、インターンシップでのアウトプットに繋がることを中心として選択できる。
企業としては、時代の流れに合わせて「インターンシップ事業」を取り入れる。『より実力や、実績が問われる時代になってくるからこそ弊社のインターンシップをすることで、採用担当が欲しくなるような実績を作ることができる。』という訴求方法で、食フェスや留学事業(海外研修)などをしてもらう。






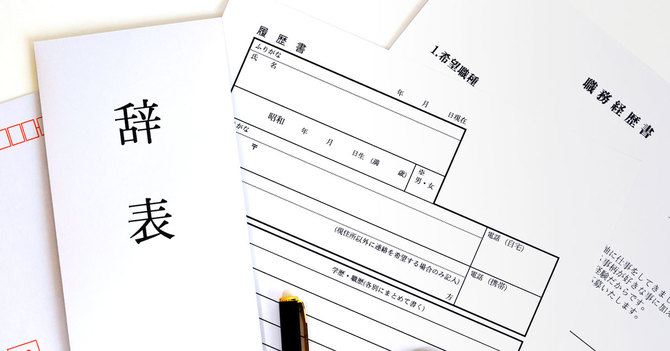

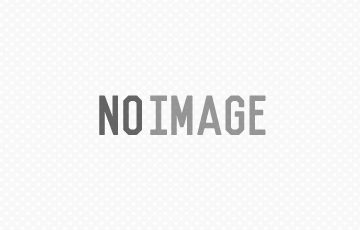

コメントを残す